妊娠中・出産後に「うつ」になった方のためのQ&A
Q7 妊娠中・出産後に「うつ」になった方のためのQ&A
-
7-1 妊娠中に「うつ」になったのではと心配しています。「うつ」とはどのようなものですか?
7-1 「 うつ状態」とは、こころ(精神)のエネルギーが全体的に下がった状態です。1日中気持ちが沈んだり、楽しいことが楽しいと思えなくなったりする状態が長く続きます。
アドバイス
- 下記の質問を使って「うつ状態」かどう、チェックしてみるとよいでしょう。どちらかひとつでも「はい」であった場合、「うつ状態」になっている可能性があります。
① この1か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。 はい いいえ ② この1か月間、どうも物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。 はい いいえ - 気持ちがつらい時は、早めに保健センターの保健師または心療内科や精神科の医師などに相談してみるとよいでしょう。

説明
- うつ状態とは、精神機能の3つの領域である「気分・思考・行動」のいずれも低下する状態です。しばしば、睡眠障害や食欲異常(食欲低下や過食など)を伴います。上記のセルフチェックは、うつ病の二大症状である持続する抑うつ気分、持続する興味・喜びの消失についてたずねるものです。(Q12-1もご覧下さい)

-
7-2 妊娠中に「うつ」になった本人は、どのようなことに気をつければよいですか?
7-2 「仕事や家事などの負担を減らす、なるべく休む、無理をしない、信頼できる人に相談する」ということを心がけ、早めに精神科あるいは心療内科を受診するとよいでしょう。
アドバイス
- 自分自身がつらい、お子さんなどの家族の面倒を見るのが大変になっている、などが思い当たる場合は、心療内科あるいは精神科を受診したほうがよいサインです。産科医や保健センターの保健師などに相談するとよいでしょう。(Q4-1もご覧下さい)
- 「うつ」がつらくて自分から行動できない時は、信頼できる誰かに打ち明けて、産科や保健センターに連れて行ってもらうとよいでしょう。
- 「うつ状態」は周囲の方に気がつかれにくいので、あきらめずにSOS を発信して下さい。つらさを、自分から周囲の方に説明しづらい場合は、保健師や医師などから説明してもらうとよいでしょう。
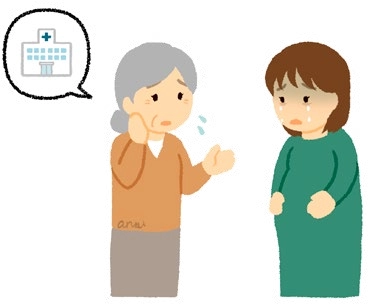
説明
- うつ状態の時は、心身のエネルギーが下がってしまっているため、がんばりたくてもがんばれません。それは怠けのせいでは決してありません。周囲の方に任せられることはできるだけ任せ、自分の負担を減らすようにするのは、甘えではなく賢い選択です。
- 休養と睡眠はうつ状態からの回復にとても大切です。周囲に迷惑をかけるなどと考えずに、休みましょう。無理をしないで早く治すことが、結果として迷惑をかけないことになります。
- 精神科などを受診した方がよい目安は、うつ状態の症状が原因で本人や周囲の方(特に子ども)の生活に支障が出ている(たとえば、元気が出なくて横になってばかりで、子どもの面倒を見てあげられない)場合です。
- 薬について心配するのは当然ですが、うつ病の薬(抗うつ薬)は、赤ちゃんにほとんど影響しません。うつ病を長引かせる方が赤ちゃんへの影響が心配です。(Q7-5もご覧下さい)
-
7-3 妊婦が「うつ」になった時、周囲のものはどうしたらよいですか?
7-3 本人のつらさをよく理解することが大切です。生活に支障がある場合は、本人につきそって心療内科あるいは精神科を受診するとよいでしょう。
アドバイス
- 妊婦の負担を減らすように工夫し、無理をさせずになるべく休んでもらい、何でも相談にのってあげるとよいでしょう。
- 精神的不調で日常生活に支障が出ている場合は、早めに精神科あるいは心療内科の受診の手はずを整えて下さい。保健センターの保健師などに相談するとよいでしょう。(Q4-1もご覧下さい)
- 本人を傷つけやすい発言の例を以下にあげます。「元気そうなのに、どうしてできないの?」「母親になるのだからもっとしっかりしなさい」「妊娠はみんな大変なの、あなただけじゃないのよ」
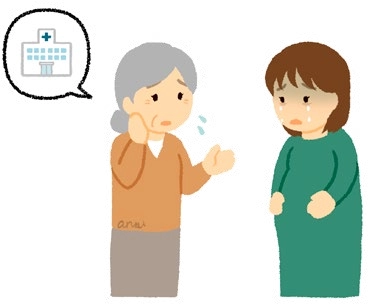
説明
- 妊婦が「うつ」になるのは珍しいことではありません。「うつ」は、決して怠けや性格の弱さなどから来るものではありません。心身のエネルギーが下がってしまっているため、がんばりたくてもがんばれない病気です。(Q12-1もご覧下さい)
- 人は困っている人を見ると、ついつい叱咤激励したり、自分自身がつらさを乗り切った経験談などを語りたくなったりします。しかし、心身のエネルギーが低くなっている状態では、はげまされても本人は思うようにできません。必要なのは、あたたかい見守りと援助です。
- こころの不調は、他人からは判断しにくく、特に若い女性は、外見に表れにくいといわれています。かつてフランスでは、若い女性のうつ病を「微笑みのうつ病」と呼ぶこともありました。したがって、本人のつらさを想像することが大切です。
- 治療のポイントは休養と服薬です。本人の負担をできるだけ減らし、休ませることが必要です。今やらなくてもよいことは、できるだけやらないままにしておくか、本人が気にするようであれば、周囲の方が代わりにやってあげましょう。
- 「うつ」の薬は、一部を除いておなかの赤ちゃんに悪い影響を及ぼすことはほとんどありません。一方、うつ状態のままで妊娠を続けることの方が赤ちゃんに悪い影響が出る可能性があります。心療内科あるいは精神科医と相談することが大切です。
(Q7-5もご覧下さい) - 産前産後は、保健センターの保健師もいろいろな困りごとの相談にのってくれます。様々な支援があります。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)
-
7-4 妊娠中に「うつ」になりましたが、精神科を受診した方がよいですか?
7-4 心配な時は早めに受診するとよいでしょう。
アドバイス
- つらい時は、早めに精神科を受診するとよいでしょう。

説明
- 受診したほうがよいか迷う時は、地域の保健センターの保健師などに相談するとよいでしょう。
- すべての場合で精神科を受診しないといけないわけではありません。「うつ」の症状が原因で、日常生活や家族(特に子ども)の生活に支障が出ている場合(たとえば、横になってばかりで、子どもの面倒を見てあげられない)などは、受診を考えるとよいでしょう。
- 薬について心配するのは当然ですが、うつ病を長引かせる方が、うつ病の薬を飲むことよりもおなかの赤ちゃんへ影響する可能性が高いと言えます。(Q7-5もご覧下さい)
-
7-5 妊娠中に「うつ」になりましたが、薬を飲み始めてもよいですか?
7-5 妊娠中に薬の治療を始めることは可能です。
アドバイス
- 「うつ」の薬(抗うつ薬)を飲むことは、赤ちゃんにとってもメリットがあると考えられています。
- 個人差がありますので、精神科医とよく相談するとよいでしょう。

説明
- 妊娠中に薬を飲むかどうかは、そのよい点と悪い点を秤(はかり)にかけて判断します。妊娠していても飲める抗うつ薬はたくさんあります。飲むことで早く回復することが期待できます。
- 心理的治療も効果が期待できるので、薬の治療と一緒に受けることをお勧めします。
- 一般に、うつ状態が重い(強い)ほど、抗うつ薬の効果が期待できます。うつ状態の程度について医師によく判断してもらうことも大切です(自己判断は危険です)。
- 抗うつ薬の他には、睡眠薬や不安を軽くするための抗不安薬などが処方されることもあります。(Q6-4もご覧下さい)
- 抗うつ薬は、飲み始め(多くは2週間以内)や薬を増量した時に、まれに普段以上に元気になったり、不安になったり、眠れなくなったりすることがあります。このような症状が現れた場合は、すぐに処方した医師や薬剤師に連絡して下さい。
- 一部の薬は、危険とは言えませんが、赤ちゃんに影響しますので、処方する医師とよく相談して下さい(Q3-4もご覧下さい)
-
7-6 「産後うつ」とはどのような病気ですか?
7-6 産後数週~数ヶ月の間に、気持ちが落ち込む、育児が楽しくない、眠れない、疲れやすいなどの症状が現れる病気で、出産された方の10-15%にみられます。

アドバイス
- 本人の性格の弱さや、育て方などの問題ではありません。(Q7-8もご覧下さい)
- かかってしまった時に「なさけない」とか「母親失格」などと思いこまないようにしましょう。
- まずは休養を取り、すぐにかかりつけ医、保健師、産科医、精神科医などに相談するとよいでしょう。(Q4-1もご覧下さい)
- 周囲に理解者がいる場合は、その人たちのサポート(つらい気持ちを聞いてもらうことや育児や家事を代わってもらうこと)を受けるとよいでしょう。
- 薬による治療も考えてみて下さい。(Q12-6もご覧下さい)
- 行政の助けなどを得られるようにするとよいでしょう。精神科医や相談員、役所などに相談するとよいでしょう。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)
説明
- 多くの方が、「他のお母さんはできているのに、自分は育児ができていない」とか「母親として落第」などという気持ちになります。また、涙が止まらなくなる、周囲の方やお子さんに対してイライラしてしまうこともあります。これらの症状は産後ほどなく出現し、2週間以内に落ち着いてしまうこともありますが、2週間以上続いた場合は、「産後うつ」である可能性があります。
- 「産後うつ」の治療は休養が大事です。薬なども使って早めに治療をすることでしっかりよくなります。(Q7-12もご覧下さい)
-
7-7 「産後うつ」に早く気づける方法はありますか?
7-7 産後に、憂うつな気分や、楽しいことが楽しいと思えない状態がしばらく続いている場合、「産後うつ病」の可能性があります。
アドバイス
- 出産後、10%以上の人が産後うつ病になります。「産後に気持ちが沈むのはよくあること」などと安易に受け流さず、気分や意欲などの変化を見逃さないようにするとよいでしょう。
- 産後うつ病が疑われる時は、早めに保健センターの保健師に相談するとよいでしょう。
- あくまでも目安のためですが、下2 つの質問に答え、どちらかひとつでも「はい」であった場合、「うつ状態」になっている可能性があります。(Q12-1もご覧下さい)
① この1か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。 はい いいえ ② この1か月間、どうも物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。 はい いいえ 
説明
- 産後うつ病では、「一日中」つらい状態が続き、そのような状態がある程度まとまった期間続きます。一日のうちの一部の時間(たとえば朝の間など)に気持ちが沈んでいても、そのあと元気が出てきて、楽しく赤ちゃんと過ごせていたりする場合などは、産後うつ病の可能性は低いと言えます。
- 産後うつ病の時は、眠れなくなったり、反対に一日中寝込んだりしたり、食欲がなくなったり、反対に食べ過ぎたりすることがあります。
-
7-8 どんな人が「産後うつ」になりやすいのですか?予防することはできますか?
7-8 「産後うつ」には、精神状態、人間関係、経済状況やホルモンバランスの変化など様々な要因が関係していますが、ある程度予防することも可能です。
アドバイス
- もともと、うつや不安で治療受けている方は、出産まで治療を続け、なるべく症状を落ち着かせておくとよいでしょう。
- できる限り周りの人々との関係をよくし、サポートしてくれる人を見つけるとよいでしょう。
- ソーシャルワーカー、保健師、産科医、助産師、精神科医などと不安について話し合っておくとよいでしょう。
- お金の心配のある方も、ソーシャルワーカーや保健師などに相談するとよいでしょう。

説明
-
7-9 「産後うつ」かもしれないと思った時、どこに相談したらいいですか?
7-9 出産した病院・クリニック・助産院及び母子健康手帳や新生児訪問を担当している市区町村の保健センター等に相談するのがよいでしょう。
アドバイス
- すでに通院されている場合は、通院先の精神科医に直接相談するとよいでしょう。
- 出産した病院・クリニック・助産院や保健センター等他の専門家に相談してもよいでしょう。
- 当事者団体(患者会)などを活用してもよいでしょう。インターネットを使って「産後うつ」「患者会」「自助グループ」といったキーワードで検索すると近所の団体を見つけることができるかもしれません。主な自助グループには以下のようなものがあります。
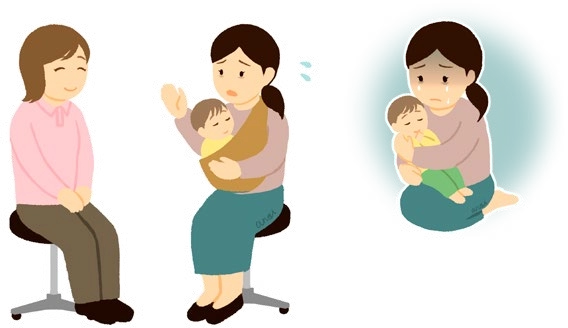
説明
- 産科医・助産師、保健センターのスタッフ、開業助産師さんなどは、産後うつ病の治療経験のある精神科医を知っている可能性が高いです。
- 開業助産師は、産後の育児の困りごとについて相談にのってくれたり、適切な授乳の仕方などについてアドバイスをくれたりします。
- 産後うつ病を経験された方々が集まって作った当事者会(患者会)という団体があります。そこでは、ピアカウンセリング(同じ悩みやつらさの経験などを持つ方々が、対等な立場で話を聞き合う)を受けることができるかもしれません。
-
7-10 「産後うつ」に対してはどのように治療してもらえますか?
7-10 精神科や心療内科などでは、お母さんが十分休めるようなサポートがあるのかどうかを確認しながら、薬の治療が必要かどうかを判断します。
アドバイス
- 「産後うつ」の治療の基本は、できるだけ休養を取ることと周囲からサポートを受けることです。
- 周囲の方に、育児や家事をサポートしてもらい、困っていることを聞いてもらうとよいでしょう。
- 育児ヘルパー(産後ヘルパー)や、各自治体で行っている産後ケア事業を利用するとよいでしょう。出産した施設や役所に問い合わせてみて下さい。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)
- 薬が必要な場合は、主に抗うつ薬が処方されます。抗うつ薬は、飲みながら母乳を与えることが可能です。(Q12-6もご覧下さい)
- 母乳が負担な場合は、周囲の方に人工乳を与えてもらっても問題ありません。(Q3-8もご覧下さい)

説明
- 育児ヘルパーは、自宅に訪問し、洗濯、掃除、買い出し、食事の準備、沐浴補助などをするサービスです。
- 産後ケア事業は、デイサービス型や宿泊型があります。宿泊型の場合、産科の病院・クリニックにて母子ともに数日間過ごし、お母さん、お子さんのケアを行います。
-
7-11 「産後うつ」に対して、周囲のものはどのような対応をしたらよいですか?
7-11 本人には「よく休むように」とアドバイスし、なるべく多くの人で仕事を分担して下さい。
アドバイス
- 本人に以下のことをしてあげるとよいでしょう。
- 休息を取らせる。
- 話を聞いてあげる。その際、こちらが一方的に思うことを伝えるのは逆効果になることがあります。また、話の内容を理解するよりも、つらい気持ちを理解することの方が大切です。
- 育児をがんばって(がんばろうとして)いることに対して、感謝の気持ちを伝える。
説明
- 「産後うつ」にかかると、自分から助けを求めることが難しくなります。話を聞いてあげる時間を十分とることで、助けを求めることができるようになったり、話すことで気持ちが楽になったりします。
- 周囲の方は、「母親なのだから育児をするのがあたりまえ」という気持ちになりがちです。一方、(特に初めて)母親になった本人は、自分がやっていることが正しいのかどうか不安になってしまうことがあります。そのような時に「大変なのに、ありがとう」というような言葉をかけられると、不安がやわらぐことがあります。
- 気持ちのつらさが強くなると、中には自分の命を投げ出したくなってしまうお母さんがいます。「死にたい」などとこぼした時には、SOS サインですので、「気を確かに持ちなさい」などとたしなめるのはよくありません。早めに医療機関や保健センターに相談しましょう。(Q10-1もご覧下さい)
- 本人に以下のことをしてあげるとよいでしょう。
-
7-12 「産後うつ」はどのくらいで良くなりますか?
7-12 適切な治療を受けると、通常1年以内に良くなります。
アドバイス
- 早めに治療を開始するとよいでしょう。
- 薬を用いた治療が必要な場合もありますが、回復後は、やめることができます。
説明
- 「産後うつ」には3-4ヶ月、6ヶ月、1年という節目があるようです。
- 産後から3~4ヶ月目までは、夜中も3 時間ごとに授乳しなければならないなど、赤ちゃんにとても手がかかる時期で、どのお母さんにとっても一番きつい時期です。3ヶ月を過ぎると、赤ちゃんの首もすわり、夜の睡眠がとれるようになりますので、お母さんの負担も少し減ってきます。また、この頃には赤ちゃんとの生活に少しずつ慣れてきます。
- 生後6ヶ月になり、寝返りができる頃になってくると、さらに一段階、気持ちが楽になります。
- 生後1年の頃には、「産後うつ」になったお母さんも、赤ちゃんの成長とともに、すっかり元どおりに回復していることが多いです。ただし、中には少し長引く方もいます。
- 一般的なうつ病の場合、抗うつ薬の治療が数年続きますが、「産後うつ」では、より早期に薬をやめられることが多いです。
-
7-13 「産後うつ」になってしまいましたが、子育ては可能ですか?
7-13 可能です。しかし「ひとり」で行おうとしない方がよいでしょう。
アドバイス
- 周囲の方に、育児や家事をサポートしてもらうとよいでしょう。
- 育児ヘルパー(産後ヘルパー)や、各自治体で行っている産後ケア事業を利用するとよいでしょう。出産した施設や役所、保健師やソーシャルワーカーに相談してみて下さい。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)
- 「産後うつ」になったお母さんをサポートする周囲の方も、つらくなったら、抱え込まずに保健師さんなどに相談しましょう。
説明
- 育児ヘルパーは、自宅に訪問し、洗濯、掃除、買い出し、食事の準備、沐浴補助などをするサービスです。
- 産後ケア事業は、デイサービス型や宿泊型があります。宿泊型の場合、産科の病院・クリニックにて母子ともに数日間過ごし、お母さん、お子さんのケアを行います。
- 「産後うつ」の治療をしている医療機関に、周囲の方などと一緒に行き、相談することもとても意味があります。皆で支え合いながら育児に取り組んでいきましょう。


