将来の妊娠を考えた生活や疾患との向き合い方に関するQ&A
Q2 将来の妊娠を考えた生活や疾患との向き合い方に関するQ&A
-
2-1 将来の妊娠を考えた生活やこころの不調や病気との向き合い方について教えて下さい。
2-1 信頼できる医療者及び行政のサービスをうまく活用するとよいでしょう。
アドバイス
- こころの不調や病気があると、妊娠・出産はできないのではないか、という不安を持つ方が多いというデータがあります。しかし、決してそんなことはありません。本ガイドの第3章にいろいろな精神疾患の方に対するアドバイスなどが載っていますのでご覧下さい。
こころの病気を抱えながら、妊娠・出産を体験された方の体験談は以下のサイトをご参照下さい。
日本うつ病学会双極性障害委員会「妊娠・出産を体験した双極性障害患者さんの事例紹介」 - くわしい内容を勉強したい方は以下の専門家向けのページをご参照下さい。(Q2-2、Q2-6もご覧下さい)
「精神疾患を合併した,或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイド:総論1 精神疾患合併または既往歴がある女性に対するプレコンセプションケア*-Shared decision making を基本姿勢として」
- プレコンセプションケアについてはQ2-2をご覧下さい。
- こころの不調や病気があると、妊娠・出産はできないのではないか、という不安を持つ方が多いというデータがあります。しかし、決してそんなことはありません。本ガイドの第3章にいろいろな精神疾患の方に対するアドバイスなどが載っていますのでご覧下さい。
-
2-2 妊娠前に精神科の薬を調整した方がよいですか?
2-2 今飲んでいる薬にもよりますが、妊娠してからも飲み続けられるように変更したほうがよいことがあります。
アドバイス
- 精神科医(心療内科医)に、妊娠を考えていることを伝えてみましょう。
- 今の薬が、妊娠してからも飲み続けられるものか、聞いてみましょう。
- 妊娠がわかった時に、自分の判断だけで、薬を中断したり、減らしたりせずに、まずは相談してみましょう。(Q3-5もご覧下さい)
- 周囲の方どなたかと一緒に、相談するとさらによいでしょう。
- かかりつけ医が妊娠前の相談に対応していないこともあります。対応してくれる医療機関を紹介してもらう、あるいは地域の精神保健福祉センターなどに相談するのもよいでしょう。(Q4-3、Q4-5もご覧下さい)

説明
- 最近では、「プレコンセプションケア」といって、こころの病気にかぎらず、妊娠する前に、妊娠のことを相談するという考えが広がっています。不安や疑問を感じたら、まずは相談してみましょう。
- 「プレコンセプションケア」とは直訳すると、「妊娠前のケア」となります。(Q2-1、Q2-4もご覧下さい)
- 現状では、かかりつけ医が「プレコンセプションケア」に対応していないことも少なくありません。薬の調整も含め、妊娠前から産後まで一時的に医療機関を変更することを勧められることもあります。(Q4-3、Q4-5もご覧下さい)
- 薬を飲んでいて妊娠に気づくこともあります。自分の判断や周囲の勧めなどで、突然薬をやめて病気が悪くなると、おなかの赤ちゃんにとっても本人にとってもよくありません。赤ちゃんの健やかな成長には、お母さんの病状が安定していることが大切です。治療方針で納得のいかない時も、自分の判断で受診を中断せず、産科や精神科の医師との話し合いを続けてみましょう。(Q3-1もご覧下さい)
-
2-3 子どもにこころの病気(精神疾患)が遺伝しないか心配です。
2-3 遺伝カウンセリング体制の整った施設で相談してみましょう。
アドバイス
- ネットの情報に振り回されないようにしましょう。
- 日本精神神経学会のウェブサイトに『石塚佳奈子先生・夏苅郁子先生・尾崎紀夫先生に「こころの病気と遺伝」を訊く』というページがありますので、読んでみるとよいでしょう。
- 昔から、血のつながりといわれるように、子どもは親に似るものです。それは、こころの病気だけではなく体の病気でも同じことがいえます。一方で、こころの病気の親をもつ子どもが、必ずこころの病気になるわけではないこともわかっています。
- こうした疑問や不安を個別に相談する方法として、‘遺伝カウンセリング’があります。体制の整った施設での相談をお勧めします。担当医におたずねになるか、以下のサイトで相談できる施設をお探し下さい。
登録機関遺伝子医療体制検索・提供システム (idenshiiryoubumon.org)
説明
- ネットでは出生前検査、着床前検査という検索で様々な情報が見つかります。しかし、誤解を招くものもあり、以下のように信頼できるサイトにアクセスすることが大切です。
「一緒に考えよう、お腹の赤ちゃんの検査」 - こころの病気の多くは、糖尿病や高血圧などの生活習慣病と同じように、多因子遺伝による多因子疾患として知られています。つまり、遺伝情報だけでなく、環境因子などが様々に組み合わさって、初めて発症すると考えられています。くわしくは「こころの病気と遺伝」のウェブサイトをお読み下さい。
- こころの病気は症状に基づいて診断されますが、特定の診断をされた方々の中には、様々な原因による方がまざっています。最近の研究から、一部の患者さんでは発症のリスクを高めるゲノム(「こころの病気と遺伝」のウェブサイトをご参照下さい)のタイプが見つかっています。
一方で、同じゲノムのタイプを持っていても、必ずしも全員が同じこころの病気になるわけではなく、あくまで発症の可能性を高める要素の一つであると考えた方がよいでしょう。
こころの病気と遺伝に関する不安や疑問が解消されない場合には、遺伝カウンセリングで個別に相談されるとよいでしょう。 - 検査はいろいろな施設で実施されておりますが、検査で、何がどこまでわかるのか?わかったら、次はどのようにしていったらいいか、ということをきちんと伝え、また本人(たち)の自己決定を支援する流れを、遺伝カウンセリングといいます。
- 遺伝カウンセリングでは家系(血のつながりのある親族のこと)に病気の方がいるかといったことをたずねられます。
-
2-4 精神科に通院している身内(子どもなど)が妊娠を希望しています。親・養育者・周囲のものとして何かできることはあるでしょうか?
2-4 妊娠前から、本人をどう支えるかについて話し合っておくとよいでしょう。
アドバイス
- 本人と一緒に「プレコンセプションケア」(女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み)を受けてみましょう。(Q2-1、Q2-2もご覧下さい)
- 「プレコンセプションケア」は、妊娠可能な年齢の方たち全般に行われており、妊娠・出産への準備に役立つものです。
- 「プレコンセプションケア」では、妊娠しても続けられる薬への調整や、睡眠時間や食生活などの生活習慣の見直し、育児の行政サポートをどうするかなどを、本人、医療スタッフとともに検討していきます。
- 遺伝については、Q2-3をご覧下さい。
説明
- 「プレコンセプションケア」は、妊娠前からの健康管理が、次の世代の健康状態だけでなく、本人のその後の人生における健康状態も改善するという考えに基づいています。まだ日本で普及しているとはいえませんが、糖尿病などの様々な疾患を抱える人が、妊娠前に、医療機関で相談されるようになってきています。
- 妊娠に向けて、こころの病状が安定するように整えていきます。
- おなかの赤ちゃんへの影響を心配するあまり、薬を飲むことや受診を自分の判断で中断してしまうことがあります。その場合、病状の悪化のため母児ともによくない状況に陥ってしまう危険があるので、周囲の方も一緒に、精神科医と治療方針について、よく話し合っておくとよいでしょう。(Q3-1もご覧下さい)
- 禁酒、禁煙、体重管理、野菜の多い食生活、葉酸サプリメント摂取(Q3-6、Q20-7もご覧下さい)などが推奨されています。ぜひ皆さんで一緒に取り組んでみましょう。
- 育児する生活環境が清潔・安全を保っているか、本人と一緒に確認してみましょう。
- 育児にはサポートが欠かせません。周囲の方がどのようにサポートしていくか話し合っておきましょう。また役所で利用できるサポートの情報を事前に集めておくとよいでしょう。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)一時的に妊娠を見合わせたいと本人が伝えてきた場合には、避妊方法について産婦人科で適切なアドバイスを受けることができます。出産後1年以内に妊娠してしまうのは、母体の負担が大きいので避けたほうがよいといわれています。

-
2-5 症状を持ちながらの子育てに不安があります。両親にもサポートは頼みづらい状況です。今後の出産・育児について、どんな準備をしたらいいですか?
2-5 どのような行政サービスが受けられるのか、事前に情報を集めておくとよいでしょう。
アドバイス
- 育児にはサポートが欠かせません。男性の育休取得も可能となってきました。役所や信頼できる周囲の方、相談員や看護師などにも相談し、サポートやアドバイスをいただくとよいでしょう。いろいろな人に納得いくまで相談できるとよいでしょう。
- 公的に利用できるサポートもいろいろあります。事前に情報を集めておくとよいでしょう。(Q1-5、 Q4-5もご覧下さい)

説明
- 妊娠・出産・育児は女性にとって大きなライフイベントのひとつです。心身ともに負担がかかる時期でもあり、症状を安定させておくことは大切です。
- 大切なことは、自分だけで乗り切ろうとしないことです。無理して症状を悪化させてしまうと、赤ちゃんにとっても望ましいとはいえません。そのためには、様々な育児や家事などで受けられるサポートの情報を事前に得ておき、必要な時に活用するとよいでしょう。
- 地域により差がありますが、役所と医療機関が協力して、サポートする体制があります。役所の窓口(子育て世代包括支援センターなど)で相談してみるとよいでしょう。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)
- 授乳などの相談・支援が受けられる、産後ケア施設についても、役所の窓口で相談することができます。宿泊型と通所型がありますので、じょうずに利用しましょう。
- 担当の精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)や訪問看護師などがいる場合には、将来の育児のサポートについても、相談してみてもよいでしょう。
-
2-6 精神科通院中です。妊娠に向けて、自分の生活で気をつけたらいいことはありますか?
2-6 禁酒、禁煙、食生活の改善など、生活習慣を見直してみましょう。
アドバイス
- 妊娠を意識し始めたら、将来の赤ちゃんのために、健康な体づくりに取り組むきっかけとしましょう。
- バランスのとれた食生活をこころがけてみましょう。
- 受動喫煙も、赤ちゃんに悪影響を及ぼします。自分だけでなく同居している方も一緒に禁煙しましょう。
- 妊娠を考え始めたら、禁酒に取り組みましょう。(Q2-1、Q2-2もご覧下さい)
- 生活習慣の見直しや改善は、ひとりでは難しいこともあります。できるだけ周囲の方と一緒に妊娠という目標に向かって取り組んでみるとよいでしょう。

説明
- 一般的に、やせ体格では、早産などのリスクが高くなるといわれています。日本では、若い女性にやせ体格が増加していることが問題となっています。反対に、肥満の体格の方では、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの様々な妊娠合併症にかかる確率が高くなります。食生活や運動などの生活習慣を見直してみましょう。
- バランスのとれた食事については、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている「健やかな体づくりと食生活BOOK」を参考にするとよいでしょう。ご自分の体格がどのくらいなのかについて計算する式ものっていますので、興味がある方は一度チェックしてみるとよいでしょう。
よりくわしく勉強されたい場合には、「妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針」も参考にしてみて下さい。 - 妊娠前の自己チェックリスト(下記表)もご覧下さい。もしも心配なことが見つかりましたら、医療機関で相談してみるとよいでしょう。

妊娠前の自己チェックリスト
- 健康的な自分自身と将来の赤ちゃんのためへのステップ妊娠について、具体的に、計画を立てましょう。
- 食生活では、野菜の摂取を心がけましょう。
- 規則的な運動習慣を身につけましょう。
- 毎日葉酸0.4mgを摂取しましょう。
- 妊娠を考えないときにはコンドームの使用などをして、性行為の際の感染症を予防しましょう。
- インフルエンザなどの感染を予防するために、手洗いやうがいなどの習慣をつけましょう。
- お酒などの身近にある有害な物質について知識を得るようにしましょう。
- 必要な予防接種を受けていない場合などは、予防接種を受けるようにしましょう。
- ストレスを減らしてメンタルを安定させるように心がけましょう。
- 喫煙をやめましょう。
- 処方通りに薬を飲んで、薬の疑問は医師に相談しましょう。他人に処方された薬は絶対に飲まないようにしましょう。
- 妊娠しようと思ったときから、飲酒はやめましょう。
- 周囲の方から暴力や虐待を受けているならば、自分で抱え込まずに、他のだれかや医師などに相談しましょう。
- 喘息、糖尿病、肥満などの身体の病気もある場合は、そちらの治療などきちんとしていきましょう。
- 自分の家族がかかったことのある病気について知っておきましょう。
- 定期的に健康診断を受け、通院している方は、必要な検査を定期的に受けましょう。
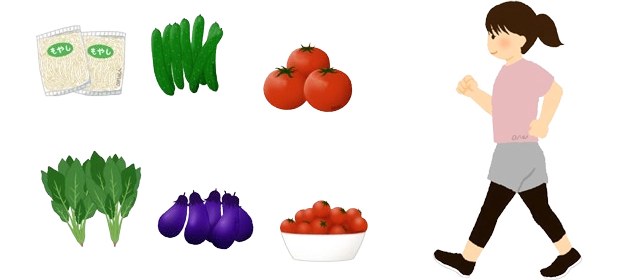
- (参考)専門家向けに以下のガイドがあります。
「精神疾患を合併した,或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイド:総論1 精神疾患合併または既往歴がある女性に対するプレコンセプションケア*-Shared decision makingを基本姿勢として」
-
2-7 こころの病気の診断を受けていても(こころの不調を抱えながら)、近くの産科クリニックで出産して大丈夫でしょうか?
2-7 産科と精神科のある施設での出産をお勧めします。
アドバイス
- 安心して出産・育児を行うために、産科と精神科の連携(協力体制)のある分娩施設を探しておくとよいでしょう。(Q4-4もご覧下さい)
説明
- 安心して出産・育児を行うためには、出産をサポートする産婦人科のスタッフ(医師や助産師など)にも、こころの病気について、しっかり知っておいてもらうことが大切です。
- 安心して出産・育児を行うためには、妊娠が順調か、出産がいつくらいになるのかなどについて、精神科の担当医に、しっかり知っておいてもらうことが大切です。(Q2-6もご覧下さい)
- 連携というのは、お互いが診療に必要な情報をやりとりすることをいいます。書面、口頭、対面などの方法で行っています。
- 地域によっては、近くに、精神科・産婦人科連携のある施設がないこともあります。妊婦健診は頻回に受診が必要です(おおよその目安は、初期~妊娠23週まで4週に1回、24週~35週まで2週に1回、妊娠36週以降出産まで週に1回となります)。事前にある程度探しておいて、妊娠前に相談しておくとより安心できることと思います。
- 実際の体験談も参考にしてみて下さい。
日本うつ病学会双極性障害委員会「妊娠・出産を体験した双極性障害患者さんの事例紹介」
-
2-8 妊娠することを、精神科の担当医に反対されるのではという不安があります。どうしたらいいでしょうか。
2-8 信頼できる誰かと一緒に、担当医と話し合う機会をもつとよいでしょう
アドバイス
- 妊娠を希望していることを精神科医に伝えましょう。
- できればパートナーあるいは周囲のどなたかとともに、妊娠・出産・育児において、精神科医として心配している点があるかどうか聞いてみるとよいでしょう。
- 妊娠前に薬の調整などを相談してみましょう。(Q2-2、Q3-1もご覧下さい)

説明
- 誰でも、妊娠を希望することは権利として認められています。「すべてのカップルと個人が性と生殖に関して自己決定でき、そのために必要な情報や手段などを得ることができる権利」のことを「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」といいます。
- プレコンセプションケアを含めた行政の相談窓口として、「性と健康の相談センター」が設置されており、厚生労働省のサイトで確認できます。
- 病気を抱えている場合には、その病気や状態にもよりますが、妊娠・出産・育児で注意すべきことがありますし、周囲のサポートも必要となります。あらかじめ、そうしたことを、担当医や周囲の方たちと話し合っておくとよいでしょう。
- 最近では、一方的に担当医が決めた治療法に従うというのではなく、本人・周囲の方とともに、方針を決めていくという考え方が広がっています(シェアードディシジョンメイキング, Shared decision making:双方向で方針を決めること)。自分の希望や考えをしっかり伝えていくことも大切なことです。
- 現在使用している薬が妊娠しにくい作用がある、あるいはおなかの赤ちゃんに影響があるものかもしれません。まずは薬の調整をお願いしてみましょう。(Q2-2、Q3-1もご覧下さい)
-
2-9 自分のこころの病気のことを産科医にも伝えなくてはいけないのでしょうか?
2-9 ぜひ伝えて下さい。安全な出産・育児へのサポートに大変大切な情報です。
アドバイス
- こころの病気にかぎらず、今まで経験した病気、今もかかっている病気はすべて、産科の担当医や助産師に伝えましょう。あるいは問診票に記載しましょう。

説明
-
2-10 こころの病気と診断されています(あるいは以前に診断されたことがあります)が、不妊治療を受ける場合に注意することはありますか?
2-10 こころの病気と診断されている(されたことがある)こと を伝えましょう。また精神科の担当医にも不妊治療を開始 することを伝えましょう。
アドバイス
- 現在通院中(あるいは以前通院していた)の精神科の担当医に、不妊治療を開始することを伝えましょう。また不妊治療施設への紹介状(診療情報提供書)を作成してもらいましょう。
- こころの病気にかぎらず、今まで経験した病気、今もかかっている病気は、すべて不妊治療の担当医に伝えましょう。あるいは問診票に記載しましょう。

説明
- 現在飲んでいる薬の中に、排卵を起こしにくくする(妊娠しづらい)ものが含まれているかもしれません。おなかの赤ちゃんに影響の出る薬が処方されていることもあるかもしれません。(Q3-1もご覧下さい)
- 不妊治療のことを伝えることで、妊娠に向けた薬の調整をするきっかけとなることがあります(Q2-2、Q3-1もご覧下さい)
- 治療を続けてもなかなか妊娠にいたらないことが、こころの不調の原因となることもあります。妊娠に向けて、こころの安定をはかるため、精神科で相談してみましょう。
- 不妊治療を行っている施設の多くは、妊婦健診や分娩は行っていません。妊娠したら、産科と精神科のある施設などへ紹介してもらうようにしましょう。(Q4-4もご覧下さい)


