「てんかん」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ&A
Q20 「てんかん」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ&A
-
20-1 てんかんにかかっていますが、出産や子育ては可能ですか?
20-1 可能です。
アドバイス
- てんかん発作が止まっている場合はもちろん、少々発作が起こっていても、出産や子育ては可能です。てんかんの薬を飲みながら、元気な赤ちゃんを産み育てている方が大勢います。
- 妊娠する前からの準備(薬を調整しておく、葉酸を飲み始めるなど)について、てんかんの治療医とあらかじめ相談しておくとよいです。妊娠に気がついた後であっても、てんかんの治療医と相談するとよいです。(Q2-2、Q20-4、Q20-5、Q20-7もご覧下さい)
- 思いがけず妊娠に気がついた時には、自己判断で薬をやめないで、早めにてんかんの治療医と相談して下さい。(Q3-1、Q20-3もご覧下さい)
- お子さんが先々てんかんにならないかというご心配に関しては、下の説明をご覧下さい。
説明
- てんかんは頻度の多い病気です。健康なお母さんから生まれた子どもであっても、おおよそ100人に1人(1%)は先々てんかんを発症します。てんかんにはいろいろなタイプがあり、てんかんのお母さんから生まれた子どもが病気になる可能性はそれぞれによって異なります。1%と変わらない場合と、そうでない場合があります。(Q2-3をご覧下さい)
- てんかんを持つ方の妊娠・出産について調べた報告は数多くあります。それによると、てんかんを持つ方は、流産、妊娠高血圧症候群(以前「妊娠中毒症」と言われていたもの)、早産、帝王切開による出産などが、そうでない方に比べて、わずかに多いですが、著しい差はありません。
- てんかんの治療医は、本人と話し合いながら薬を処方し続け、妊娠中に強い発作が起こらないようにします。(Q20-5もご覧下さい)
- 薬による赤ちゃんへの影響はQ20-3を、薬の調整についてはQ20-4、Q20-5、Q20-6をご覧下さい。
- 妊娠の前から葉酸を飲んでおくと、赤ちゃんに多くのメリットが期待できます(Q20-7もご覧下さい)。
-
20-2 妊娠中にてんかん発作が起こると、お母さんやおなかの赤ちゃんに危険がありますか?
20-2 弱い発作であれば危険はありません。強い発作だと、多少の危険があります。
アドバイス
- 妊娠中に、強い発作が起こらないようにすることが大切です。
- 妊娠中に、自己判断で薬を飲むのをやめてしまうと、強い発作が起こりやすくなり危険です。
- 妊娠に気がついたら、てんかんの薬を処方している医師に早めに伝え、よく相談して下さい。
- 妊娠する前から、薬を飲むことのメリットとデメリットについて、担当医とよく話し合っておくとよいでしょう。
説明
- 最も強いてんかん発作の場合、倒れて、全身が2~3分ほどけいれんします。その間は普通の呼吸ができなくなり酸素が不足します。そのため、妊娠していた場合、おなかの赤ちゃんにも負担がかかります。また、けいれん中は、おなかに強く圧がかかるため、流産する可能性等もあります。
- 中程度のてんかん発作のひとつの例では、けいれんは起こらないものの、意識を失って転倒します。倒れる際に、打ちどころが悪かったりすると、おなかの赤ちゃんに負担がかかります。
- 弱いてんかん発作のひとつの例では、けいれんはなく意識も失わず、少しだけ気持ち悪くなったりします。この場合は、お母さんとおなかの赤ちゃんの両方に、危険はまったくありません。
-
20-3 妊娠中にてんかんの薬を飲むと、子どもにどんな影響がありますか?
20-3 一部の薬は、赤ちゃんの形態あるいは精神の発達に影響を及ぼす可能性があります。
アドバイス
- 薬の赤ちゃんへの影響は、その種類や量によって異なります。一部には影響のある薬もあり、量が多くなると影響が出る薬もあります。てんかんの薬を処方している医師や薬剤師などと相談するとよいでしょう。
- 薬をやめると、強い発作が起こることがあり危険です。自己判断で薬をやめたり減らしたりすることはしないで下さい。
- もともとのてんかん発作が軽く、かつ発作が長く止まっている方は、薬をやめられるかもしれませんが、それでも自己判断で薬を調整せずに医師に相談して下さい。
- てんかんの薬を処方している医師がてんかんの専門の医師でない場合、日本てんかん学会専門医やてんかんの治療にくわしい医師を紹介してもらうとよいでしょう。
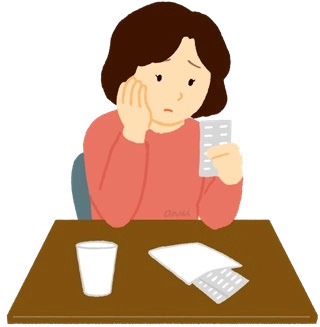
説明
- どんなお母さんの場合でも、赤ちゃんに形態の異常が生じたり、精神の発達が遅れたりするなどの可能性があります。(これをベースラインリスクといいます。)
- 形態の異常に関するベースラインリスクは、おおよそ3%です。(Q1-6もご覧下さい)
- 過去には、妊娠中にてんかんの薬を飲んでいると、形態異常のリスクが高くなることが問題となっていました。しかし、最近20~30年の調査によって、どの薬をどの程度の量使うと、形態異常を引き起こしやすいか、逆にいうと、どうすれば、そのリスクを下げられるかについて、くわしくわかってきています。精神の発達の障害に対するリスクも同様に低く抑えることが可能になってきています。
- 時に誤解されますが、妊娠する以前に飲んでいたてんかんの薬は、赤ちゃんに影響しません。飲むのをやめた薬は、数日から遅くても数週間経てば、体の中にほとんど残っていません。
-
20-4 妊娠中に飲むのに適しているてんかんの薬には、どのようなものがありますか?
20-4 どの薬という特定のものではなく、発作(特に強い発作)を抑え、かつ赤ちゃんへの影響ができるだけ小さいものが、適しているといえます。
アドバイス
- 薬について、できれば妊娠前から、妊娠した後でも遅くないので、処方している医師と相談するとよいでしょう。
(Q2-2もご覧下さい) - バルプロ酸(デパケン、バレリン、セレニカ、バルプロ酸ナトリウム)を飲んでいる場合、それが妊娠に適した処方なのかどうか、変更しなくてよいのかどうか、医師に確認してみましょう。(それが適した処方のこともあります。)(Q3-1もご覧下さい)
- 薬は、自己判断でやめたり減らしたりせず、不安があったら処方している医師や薬剤師に相談するとよいでしょう。

説明
- 妊娠中に強いてんかん発作が起こることは避けるべきです。妊娠中の薬の調整の原則は、強い発作を予防し、かつ赤ちゃんへの影響を小さくすることです。
- 病状が軽い場合には、赤ちゃんへの影響が小さい薬を少量飲むだけでよいかもしれませんが、病状が重い場合は、2種類以上の薬を多量に飲むこともあります。つまり「妊娠に適した処方」は、人によって異なります。
- 最近、妊娠中の女性に最も多く使われているてんかんの薬は、レベチラセタム(イーケプラ)とラモトリギン(ラミクタール)です。この2つは、赤ちゃんへの影響が非常に小さいことが確かめられています。近年、妊娠可能年齢の女性にてんかん治療を開始する場合、この2つのどちらかで始めることが多くなってきています。
- レベチラセタム(イーケプラ)とラモトリギン(ラミクタール)は多くの方で発作を抑えることができますが、この2つでは発作が抑えられない、あるいは副作用で使えない場合があります。また、すでに赤ちゃんへのリスクが大きくない薬で発作が抑えられている場合には、それをわざわざ変更することにメリットがあるのかどうかは慎重に考えるべきです。
- 薬は、飲む量も大切です。バルプロ酸(デパケン、バレリン、セレニカ、バルプロ酸ナトリウム)、カルバマゼピン(テグレトール、テレスミン)、フェノバルビタール(フェノバール)、ラモトリギン(ラミクタール)のおなかの赤ちゃんへの影響は、量が多いほど強いことがわかっています。なるべく少ない量で発作を抑えることが大切です。
- 薬の種類を少なくした方が、赤ちゃんへのリスクを下げることができるのですが、1種類の薬で発作が十分に抑えられない時には、2種類あるいはそれ以上の薬が使われます。
- バルプロ酸(デパケン、バレリン、セレニカ、バルプロ酸ナトリウム)は、赤ちゃんの形態及び発達の障害を引き起こす可能性があり、特に量が多くなると、そのリスクは高くなります。しかし、一方で、この薬は強いけいれん発作を抑える効果がとても強く、他の薬では発作が抑えられないという患者さんもいます。その場合は、バルプロ酸を飲みながら妊娠、出産するという選択肢もあります。バルプロ酸は、量が少なければ、リスクは低くなり、少ない量のバルプロ酸で発作がぴたりと止まるということがしばしばあります。バルプロ酸を減らすことを試みるかどうかは、医師とよく相談して決めましょう。妊娠前に相談しておくことが理想です。
- 薬について、できれば妊娠前から、妊娠した後でも遅くないので、処方している医師と相談するとよいでしょう。
-
20-5 てんかんの薬を、妊娠に適した処方に変える方法について教えて下さい。
20-5 可能であれば妊娠前から、妊娠判明後であっても、できるだけ早い時期から、本人・周囲の方と医師とで話し合いつつ慎重に行います。
アドバイス
- 妊娠を具体的に考え始めた時、あるいはその前から、てんかんの治療医に相談するとよいでしょう。
- 薬を飲む本人と処方する医師との共同作業で行いますので、よく話し合うとよいでしょう。
説明
- 妊娠に適した処方とは、強い発作が起こることを防ぎ、赤ちゃんへの影響ができるだけ少ないものです。具体的には以下のように行います。(Q20-4もご覧下さい)
- なるべく赤ちゃんへの影響が少ない薬を使う(バルプロ酸はできるだけ避ける。)
- できるだけ少量を使う
- なるべく1種類の薬を使う。それで発作が抑えられなければ、複数の種類の薬を使う。
- バルプロ酸を使わないと発作が抑えられない場合は、できるだけ少量(1日500~600㎎以下)を使う
- 薬の調整は、できれば妊娠前に時間をかけて行うとよいです。薬を急に変えると、強い発作が起こってしまうかもしれません。それが妊娠中に起こってしまうと、お母さんにとっても妊娠前に起こるより危険な場合があります。
- 薬の調整にかかる期間は、場合によっては年単位になってしまうこともあります。赤ちゃんへの影響が少ない薬を試して、発作が抑えられれば、それで調整は完了です。しかし、実際には試行錯誤が必要です。ですから、医師と相談のうえ、なるべく早くから調整し始めると安心です。(Q2-2もご覧下さい)

-
20-6 てんかんの薬を、妊娠に適した処方に変えていく場合、薬を飲む本人は、どのようなことに注意したらよいですか?
20-6 発作の程度や回数及び体や心の調子に変わりがないか注意して下さい。どんなことでも医師にお話しして下さい。
アドバイス
- 妊娠に適した処方に変えていくのは、医師と本人との共同作業です。薬の効き方、副作用の出方は人によって異なります。ですから、もし発作の回数が増えたり、体や心の調子が変化したりしたら、どんなことでも薬を処方した医師に相談するとよいでしょう。(Q2-2もご覧下さい)
- 月経困難症、不妊治療などで女性ホルモンを服用する方は、てんかんの薬を処方している医師に伝えて下さい。一部のてんかんの薬と女性ホルモンがお互いに影響することがあります。
- 体重、血圧などの変化を記録するとよいでしょう。(Q2-6もご覧下さい)
- 薬の血中濃度や、感じることのできない副作用を事前に知るために血液検査などを受けるとよいでしょう。
説明
- 妊娠中は、お母さんの体の中で薬を分解する力が強まります。そのため、同じ量の薬を飲んでいても、妊娠中にてんかんの薬が効かなくなって発作が起きてしまうことがあります。ラモトリギン(ラミクタール)などの薬で知られていることです。そのようなことを防ぐ手段として、血液検査で薬が効いているのかどうかを、ある程度予想することができます。
-
20-7 てんかんの薬を飲みながら妊娠する場合、葉酸を飲んだ方がよいですか?
20-7 飲むことをお勧めします。
アドバイス
- 妊娠前から、緑黄色野菜など葉酸を豊富に含む食べ物を食べるように心がけるとよいでしょう。
- 妊娠中及び授乳中は普段よりもたくさんの葉酸が必要になるので、サプリメントなどで葉酸を補うのもよいでしょう。
- 葉酸は、妊娠する3ケ月以上前から飲み始めるのが最も効果的といわれていますが、妊娠してからでも遅くないので、早めに飲み始めるとよいでしょう。
- 飲む量は、少量(1日0.4mg程度)をお勧めします。

説明
- 葉酸は緑黄色野菜などに多く含まれているビタミンBの一種で、体の成長や修復に大切な働きをしています。
- おなかの中で、赤ちゃんの体が作られていく時には、たくさんの葉酸が必要になります。日本の妊娠可能年齢の女性は、普段から葉酸が不足しているといわれています。そこで食べ物以外にも、サプリメントで葉酸を補うとよいでしょう。厚生労働省は、一般の妊娠可能女性にも、妊娠前から妊娠初期まで、1日0.4mgの葉酸補充を勧めています。
- 葉酸は、飲み始めて、すぐには効果が出にくいので、妊娠する3ケ月以上前から飲むのが理想的です。葉酸は、毎日飲み続けると効果的です。
- てんかんの薬を飲んでいない女性についてですが、妊娠中に葉酸を十分にとっていると、自然流産、赤ちゃんの形態異常、発達障害(神経発達症)などが起こりにくいことが確かめられています。てんかんの薬を飲んでいる女性についても、これらの効果の一部が確認されています。
- てんかんの薬を飲んでいる場合に、葉酸をどのくらいの量飲むべきかについて、妊娠前から妊娠初期までは、世界的にまだ定まった意見がなく、少量(1日0.4mg程度)から多量(1日4~5mg)まで意見が分かれています。妊娠中期以降は、少量が推奨されています。日本では、妊娠前から妊娠中及び授乳終了まで、1日に0.4~0.6mg程度の少量が勧められています。
参考
専門家向けには以下のサイトがあります。
精神疾患を合併した、或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイド.各論12妊産婦と向精神薬 -
20-8 産科とてんかんの治療をする医師は、どのように連携するのですか?
20-8 紹介状(診療情報提供書)が基本です。
アドバイス
- 妊娠したことがわかったら、それをてんかんの治療医に伝え、産科医にてんかんについての情報を伝えてもらって下さい。紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうとよいでしょう。(Q4-4もご覧下さい)
- てんかんの治療医にも、出産に適した病院について相談するとよいでしょう。
- 産科医に、てんかんの治療医からの紹介状(診療情報提供書)を見せ、自分が、その病院での出産が可能かどうか相談するとよいでしょう。(Q2-7もご覧下さい)
- 妊娠中は、てんかんの病状の変化や薬の変更などについて産科医に伝え、逆に、妊娠の経過について、てんかんの治療医に伝えるとよいでしょう。
説明
- 妊娠・出産を安全に行うためには、いつごろからどういう発作があったか、ここ1~2年どのような発作がどのくらい起こっているのか、薬の内容、てんかんの発作が起こった時の対応法など、てんかんに関する情報が正確に産科に伝わることが大切です。紹介状(診療情報提供書)によってそれが可能になります。
- 産科医が、紹介状(診療情報提供書)の情報をもとに、自身の施設で出産可能かどうか判断します。リスクを減らすために遠方の施設を紹介されることがありますが、これは他のこころの病気、あるいは高血圧や糖尿病などの身体疾患の場合にもよくあることです。てんかんの病状が重い場合(強い発作が起こりやすい、多種・多量の薬を飲んでいるなど)は、急変時の対応や、出生した児のケアなどの点で、周産期母子医療センターや、新生児特定集中治療室(NICU)を備えた病院が安心です。
- 妊娠の途中で、病状が変化した場合には、医師同士が必要に応じて、電話や紹介状(診療情報提供書)などで連絡を取り合います。
-
20-9 てんかんの薬を飲みながら母乳をあげられますか?
20-9 はい、基本的に可能ですが、医師と相談しておくようにしましょう。
アドバイス
- てんかんの薬を飲みながら母乳を与えることは基本的に可能ですが、薬の種類や量によっては注意が必要です。出産の前から、てんかんの治療医あるいは小児科医などと相談しておくとよいでしょう。
- 特に生後2 ケ月までの間は、赤ちゃんが、何となく元気がない、ぐったりしている、うとうとしていることが多い、母乳を吸う力が弱い、体重が増えないなどのことが起こらないか注意するとよいでしょう。母乳に含まれている薬の影響の可能性もありますので、気になることがあれば、すぐにてんかんの治療医あるいは小児科医などに相談するとよいでしょう。
- 薬の影響が赤ちゃんに出ている可能性がある場合や、お母さんや周囲の方の考え方によっては、混合栄養(母乳と人工乳を交互に与える)、人工乳にすることもよいでしょう。(Q3-7、Q3-8もご覧下さい)

説明
- 多くのてんかんの薬の添付文書には、「薬物の母乳への移行が確認されているので授乳は控えて下さい」というような文言が書かれています。しかし実際には授乳はほとんど問題ありません。日本の代表的なてんかん診療ガイドラインにも、てんかんの薬を服用しながらの授乳は原則的に可能であると明記されています。ただ、てんかんの薬の種類によっては、母乳に比較的入りやすいものや、赤ちゃんの体から出るのに長い時間がかかるものなどがあります。そのような薬を多量に飲みながら母乳を与え続けると、赤ちゃんに影響が出る場合もあります。
- ご自身の薬の種類や量で授乳への影響はあるかどうかを、出産の前から、てんかんの治療医あるいは小児科医などと相談しておくとよいでしょう。
- 最近は、人工乳でも赤ちゃんに問題が生じることはないと考えられています。人工乳にすると、夜間の授乳をお母さん以外の人に代わってもらえるという利点もあります。
-
20-10 てんかんの診断を受けている本人や周囲のものは、授乳、沐浴、抱っこする時など、産後の生活でどんなことに注意すればよいですか?
20-10 もしも発作が起こっても、赤ちゃんの安全を保てるように、本人が赤ちゃんを抱くときは立たずに、周囲から硬いものを遠ざけましょう。また、発作を防ぐために、寝不足や過労をできるだけ避けましょう。
アドバイス
- 授乳は、座って、あるいは横向きに寝た姿勢で行い、周囲に柔らかい布、クッション、枕などを敷き詰めておくとよいでしょう。柔らかすぎると窒息の危険が生ずるので、ほどほどの柔らかさにして下さい。
- 本人が抱っこをする時は、座ってするとよいでしょう。泣いているのをあやす時には、思わず立ちたくなりますが、座ったままあやす方が安全です。
- 沐浴は特に注意が必要です。赤ちゃんは浅い水でも溺れてしまうので、周囲の方と一緒に沐浴するようにしましょう。
- てんかん発作は、寝不足や過労で起こりやすくなります。そこで夜は、周囲の方が人工乳をあげるなどして、本人が夜ぐっすり眠れるようにするとよいでしょう。周囲の方が、できるだけ赤ちゃんの世話をして、本人が休む時間を取れるようにしましょう。
説明


